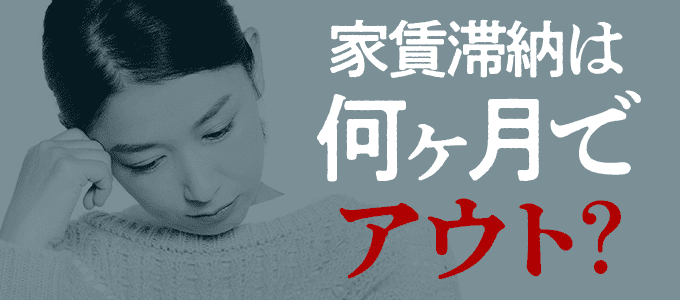
滞納して何ヶ月経つと退去になる?一般的な目安
家賃を滞納したら何ヶ月で強制退去させられてしまうのか?
これは多くの人が真っ先に抱く疑問でしょう。
結論から言えば、明確に「○ヶ月滞納したら即退去」という決まりは法律上ありません。
賃貸借契約では家賃支払いは重要な義務ですが、1回でも滞納しただけですぐに契約解除とは通常なりません。

一般的な目安として、滞納が約3ヶ月続くと強制退去のリスクが高まると言われています。
実際、3ヶ月以上家賃を滞納すると貸主(大家さん)との「信頼関係が破壊された」とみなされ、契約解除や退去要求が認められやすくなる傾向があります。
過去の判例でも、家賃2ヶ月滞納で賃貸借契約を自動的に解除するという契約条項は消費者契約法に照らして無効と判断された例があり、少なくとも2ヶ月程度の滞納では直ちに契約解除とはならないことが示唆されています。

とはいえ、「3ヶ月まで大丈夫」という意味では決してありません。
極端に言えば支払い期日を1日でも過ぎれば契約違反ではあります。
ただ、多くの場合はすぐに退去ではなく、まず督促や話し合いから始まります。
1~2ヶ月の滞納であれば猶予をもらえたり、分割払いなどで契約関係を継続できる場合もあります。

強制退去とは何か?その手続きと制限
「強制退去」とは、貸主側が法的手段を用いて借主を物件から退去させることです。
日本の法律では、貸主が勝手に借主の荷物を運び出したり、鍵を交換して締め出すような「実力行使(自力救済)」は認められていません。

具体的には、貸主が裁判所に賃貸借契約の解除と建物明け渡しの訴えを起こし、判決で借主に退去命令(明け渡し命令)が出て初めて、強制執行手続きにより退去させることが可能になります。
したがって、たとえ家賃を滞納していても、裁判を経ずに突然鍵を変えられて追い出されるようなことは本来あってはならないのです。
もしそうした行為があれば、それ自体が違法となります。

強制退去の手続きには時間と手間がかかります。
裁判の提起から判決確定、そして強制執行の申し立て・実行まで、数ヶ月から半年以上かかることもあります。
その間に滞納家賃が増え続けるのは貸主にとっても負担です。
このため多くの貸主は、できれば裁判に頼らず話し合いや任意の退去で解決したいと考えています。
しかし借主と連絡が取れない、支払いの見込みが全く立たないと判断されれば、法的手段に訴えざるをえません。
滞納が引き起こすその他のリスク

以下のような様々な悪影響が生じる可能性があります。
遅延損害金(延滞利息)の発生
賃貸借契約書には滞納時の延滞利率が定められている場合が多く、滞納日数に応じて所定の利息(年○%など)が滞納額に加算されます。
長引くほど支払総額が増えてしまいます。
保証人や保証会社への負担・迷惑
親族等の連帯保証人がいる場合、貸主や管理会社は保証人にも支払いを請求できます。
保証会社を利用している場合は保証会社が立替払いし、後日あなたに求償してきます。
いずれにせよ、自分以外の第三者に迷惑や金銭負担が及びます。
信用情報やブラックリストへの登録
滞納が一定期間続くと、金融機関の信用情報に事故情報(異動情報)として記録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまう可能性があります。
そうなるとクレジットカードの新規作成やローンが通りにくくなるリスクがあります。
今後の賃貸審査への影響
滞納によって強制退去などのトラブルを起こした履歴は、直接の信用情報機関に載らなくても賃貸保証会社間で共有されたり、業界内の情報として残る場合があります。
次に別の物件を借りようとしたとき、審査で過去の滞納歴が原因で断られる可能性も高まります。
訴訟費用等の負担
裁判になれば、未払い家賃に加えて訴訟費用や強制執行費用の一部を負担するケースもあります。
また弁護士が代理人に就くと、その弁護士費用相当額も請求に上乗せされることがあります。
精神的なストレス
督促の連絡が来る精神的プレッシャー、退去の不安、周囲(例えば保証人である親族)への後ろめたさなど、滞納はメンタルヘルスにも大きな負担となります。
実際に「夜も眠れない」「胃が痛む」などの声もネット上では見受けられます。
こうしたリスクを踏まえると、家賃滞納は「たかが滞納」と甘く見て放置してはいけない問題だと分かります。
特に強制退去は生活の拠点を失う重大事ですから、そうなる前に手を打つことが肝心です。
なお、一つ覚えておいていただきたいのは、貸主側もできれば穏便に解決したいと思っているという点です。
